三五のキャリアパス
Career path
Career path
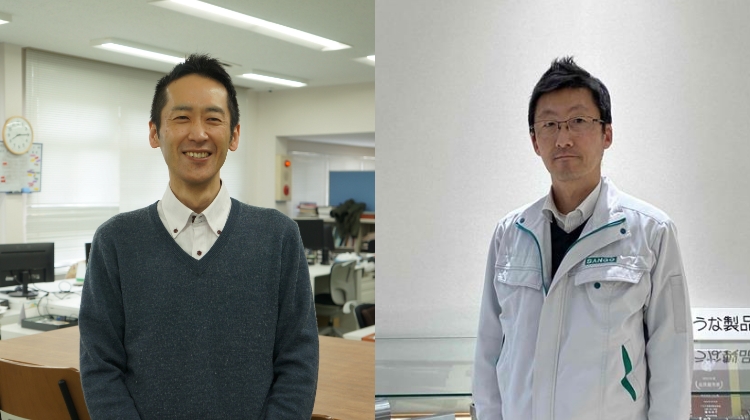
Career Models

経理財務
商学科卒
2001年入社
入社1年目
経理部
三五はグローバルに事業を展開し、トヨタをはじめとする複数の大手自動車メーカーとの安定した取引を継続。近年では新規事業にも積極的に挑戦しています。その環境下において、経理部ではお金の管理はもちろんのこと、経営に役立つ情報を提供することで会社の発展を支援。取引先との信頼構築においても重要な役割を担っています。私は経理事務職として伝票処理や補助簿管理、固定資産管理、予算管理に従事。さらに担当者として全社データの取りまとめや、全社展開用マニュアルの整備にも取り組んできました。
入社16年目
BR品目改革部/工場企画部
経理部の原価管理グループにて品番別の原価計算やレート作成を手がけた経験を活かし、BR(ビジネスリフォーム)品目改革部へ異動してからは、製品の採算性評価とその分析を担当しました。原価企画と原価管理が同じ部署に在籍していたため、原価のつくり込みを意識しながら業務を行い、工場の原価低減活動を推進。その後に工場企画部に異動した際は、工場に近い事務所に勤務することになり、工場を統括する部署で方針作成や工場損益管理に関わりながら原価低減活動を進めることができました。
入社18年目
経理・財務部
再び経理・財務部に戻り、経営判断の材料として活用する管理会計を中心とした業務を担当。セグメント損益管理と全社の利益計画策定や予算管理、固定資産管理の仕組み・ルールづくりに取り組んできました。今後は部門全体のマネジメントや経営戦略の立案に携わりながら、経営参謀として社員と経営者の仲介役を担っていきたいですね。また、ERP導入中のプロジェクトに参画しているため、複数企業(国内外事業体)の経理体制の構築や業務改善の支援、さらに内部統制整備に関して経理の専門性を活かしたいと思います。
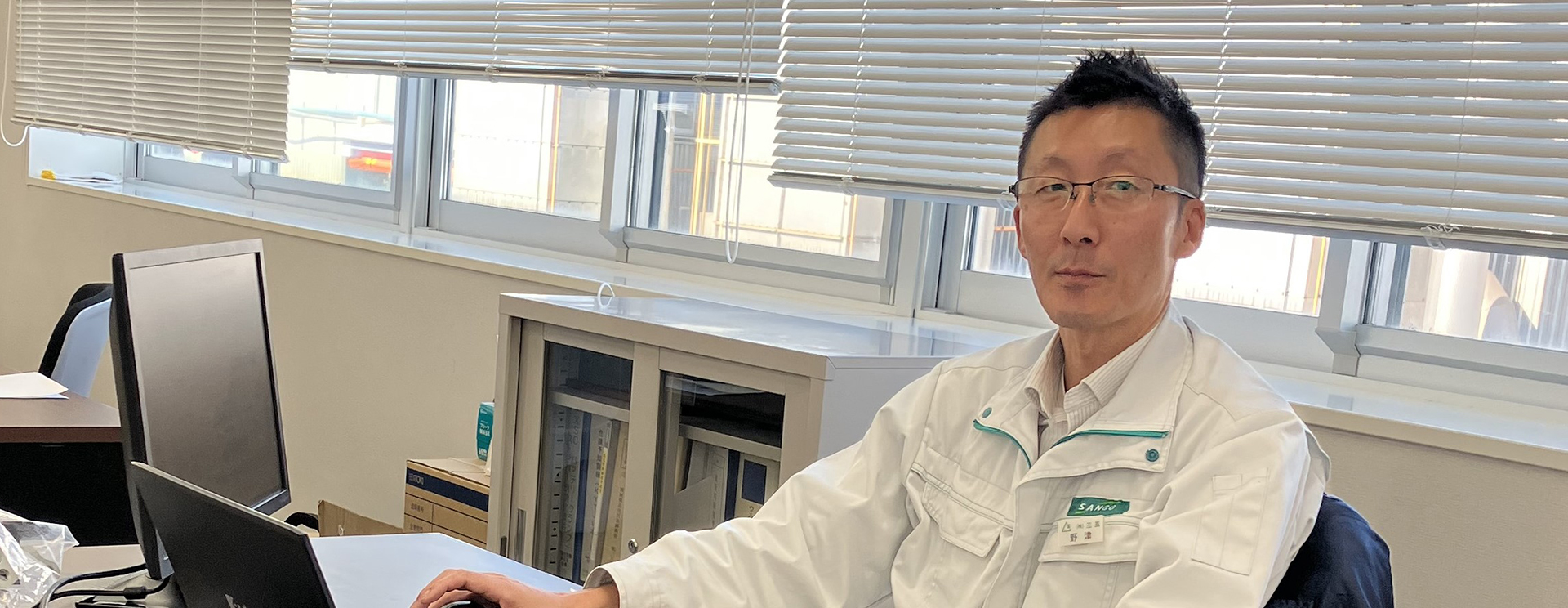
新製品・新技術開発
生物資源学科卒
2002年入社
入社1年
ボデー生技部 ボデー生技課
生産技術を学びながら新規部品の生産準備業務に従事。自動化や生産ラインのコンパクト化へのこだわりを持ち、海外での生産準備も経験しながら設備の標準化に取り組んできました。3次元測定機を使った生産準備での品質の造り込み方法を確立し、最新の産業用ロボットを使った全自動ラインを構築。また、ロボットの目とも言えるビジョンセンサや、3次元シミュレーションを使った工程設計のデジタル化にも挑みました。この時期に仕事のすすめ方をはじめ、技術者としての軸になるものが形成されたと思います。
入社10年目
先進技術室 生技開発1課
加工開発G兼生技開発2課
CVJ部品開発G
専門知識を深めるためにプレス技術部への異動を希望したところ、配属されたのはさらに川上の開発部隊。排気系製品で重要となる「パイプ曲げ」で新しい構造の曲げ型の開発を手がけ、特許取得以降、学会での発表を踏まえ、日本塑性加工学会の技術開発賞を受賞し、新しいエキマニ生産ラインに採用されました。後に鍛造を使った部品加工開発に携わるタイミングで、これまで続けてきた加工開発と兼任することに。2人の上司から指導を受け、2つのグループの運営・マネジメントを任されたことは、大きな成長につながりました。
入社18年目
ボデー精鋼開発部
精鋼・シャシー開発室
鍛造関連に特化した精鋼・シャシー開発室の発足をきっかけに部署異動。三五オリジナルの加工法「管鍛造」を打ち出し、駆動系部品や電動化に向けたモーター部品の開発に注力してきました。2024年1月に精鋼・シャシーの統括、生産技術と研究開発をまとめた新部署の部長となり、これまでの経験を幅広い領域で活かしています。自動車業界が目まぐるしく変化する中で製品形態にとらわれない、フレキシブルに対応できる加工技術の向上が当面の目標。電動化が進んでも必要とされる駆動系製品を中心に、精鋼分野のコア事業を立ち上げて部署全体をけん引したいと考えています。